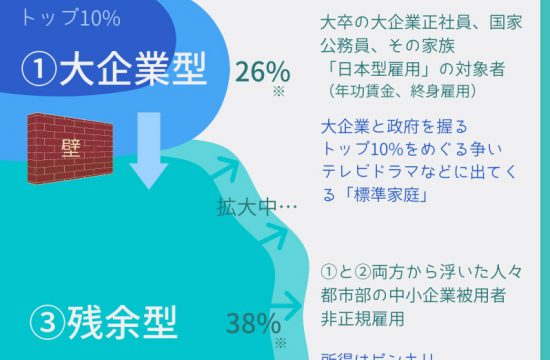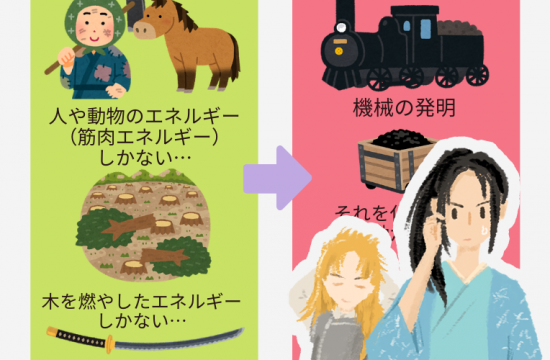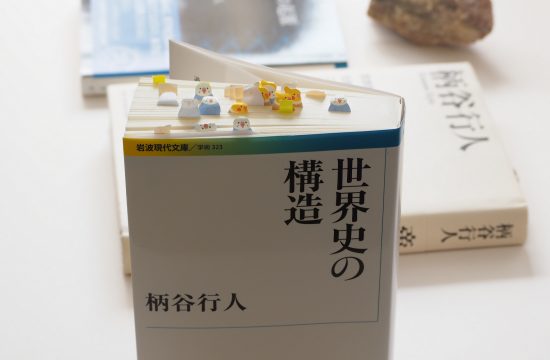白骨温泉に行きました! というのも、今年『大菩薩峠』を読了したからなのですが。

『大菩薩峠』といわれてもまったく知らない人も多いと思いますが、大正時代から戦中にかけて書き継がれ、未完に終わった長編の大衆小説です。文庫本で二十巻。現在の大衆時代小説の、「母胎」となった作品で、とくに主人公の剣客、机龍之助の虚無的な性格は、後続作品の人物造形に影響を与えました。「眠狂四郎」を生み出した柴田錬三郎さんも、はっきりと机龍之助を意識していたと書かれています。
『大菩薩峠』は、連載当時からさまざまな批評や賛辞があり、谷崎潤一郎は、泉鏡花から大正八、九年ごろに是非読むようにと勧められて、こんな文章を残しています。
兎にも角にも主人公の龍之助があれだけ書けていれば、ああ云う長編小説としては、その他の人間はタイプだけで結構である。(略)別に内面描写などがしてある訳ではないのだが、ただぼうっと場面へ出現するだけで、鬼気迫るような感じを与える。それがくだくだしい描写や説明がないだけに、一層生きているように思える。」
(『饒舌録』、ただし『果てもない道中記』からの孫引用)

ところで、今回泊まった宿は湯元齋藤旅館。
中里介山も宿泊して、物語中盤、白骨温泉を舞台にした巻の構想を得たという老舗旅館です。お湯が素晴らしかった! ぬるーい露天風呂があるのですが、その晩は冷たい雨がそぼ降っていて、四十分位入っていたけどだーれも来なくて、貸切でした……。四種類のお風呂を全制覇、一泊二日で五回入浴! そのせいかもしれませんが、帰ってからも三日くらい、ふとした拍子に髪や体から気持ちよく硫黄のにおいがして、白骨温泉のお湯のちからに驚きました。
しかし、まあ、後で詳しく書きますが、『大菩薩峠』を知りたかったら、本編を読むより安岡章太郎『果てもない道中記』(上下巻)を読むことを強くおすすめします(笑)。とくに本編の、あの、無駄に長い最後の数巻は、時代小説の熱烈なファンでもなければ、絶対に耐えられません。
『果てもない道中記』は、胆石と心筋梗塞で死にかけた著者の、病床の読書日記みたいな本ですが、『大菩薩峠』の筋を丁寧に追い、印象的なシーンをふんだんに引用し、さらに詳しい解説を加えてあります。文章が水のように読みやすいうえ、『大菩薩峠』自体が無類に面白い話でもあるので、寝食忘れてとまではいきませんが、一気に読み通してしまいました。
たとえば物語の冒頭、大菩薩峠で机龍之助が行きずりの老巡礼を斬り捨てるシーン(リンク先は青空文庫)。ここ、原作の文章はあっけないくらいに少ないのですが……。
歳は三十の前後、細面で色は白く、身は痩せているが骨格は冴えています。この若い武士が峠の上に立つと、ゴーッと、青嵐が崩れる。(略)
不意に背後(うしろ)から人の足音が起ります。
「老爺(おやじ)」
それはさいぜんの武士でありました。
「はい」
老爺は、あわただしく居ずまいを直して挨拶をしようとする時、かの武士は前後を見廻して、
「ここへ出ろ」
編笠も取らず、用事をも言わず、小手招(こてまね)きするので、巡礼の老爺は怖る怖る、
「はい、何ぞ御用でござりまするか」
小腰をかがめて進み寄ると、
「あっちへ向け」
この声もろともに、パッと血煙が立つと見れば、なんという無残なことでしょう、あっという間もなく、胴体全く二つになって青草の上にのめってしまいました。(『第一巻 甲源一刀流の巻』)
読者にしてみればいきなり「………え?」てなもんです。
さらに、物語は次から次へと展開、第一巻を半分も読んだ頃には、冒頭で名もない老巡礼が無意味に殺害されたことなど、すっかり忘れてしまいそうに………。いや、それが、そうでもないのです。この冒頭は、机龍之助という主人公の「核(=虚無)」を表現している、きわめて印象的なシーンで、読み進めるほど、じわじわ効いてくるものがあります。『果てもない道中記』は、こんなふうに解説しています。
(『果てもなき道中記』上巻)
もっとも、『大菩薩峠』は因果応報話ではありません。そもそもは、四巻目くらいで龍之助が兵馬に討たれて終わる、仇討ち話だったようですが、物語が動き始めると作者自身にも止められなくなり、やたら難解な前書きがこうです。
安岡正太郎いわく、「ちんぷんかんぷんである。ただ私は、そこにわれわれの意識下に沈んだ内的な世界を感じ、作者がそれを小説のかたちで映し出そうとしていることは、何とか汲み取れるのである」。個人的には、人間が頭で考える単純な善悪を超えたところにある、「カルマの諸相」みたいなものを描きたかったのかな、と思います。
さて、机龍之助の身の上に知らず降りかかってきた「人間界の諸相の中で、殊更にまがまがしいもの」、その最初の使者こそ、妻になる「お浜」です。ここがまた、原作は「え?」っていうくらいあっさり書かれているんですが、安岡章太郎によって、島尾敏雄『死の棘』などを引きながら、じっくり書かれた解説では、お浜という女の怖ろしさ、健気さ、情愛の深さ、しかし、やっぱり怖ろしさが、よーく味わえるようになっています。ほんの一部分を抜粋すると、
(『果てもない道中記』上巻)
安岡は、介山のなかには「女性嫌悪ないし恐怖があって、龍之助の骨を刺すような冷酷さも、そこから出ているのではないか」と述べています。それは当たっていると思いますが、私は、物語後半に、お雪ちゃんやお松のような肯定的な女性が登場してくるのを見ると、こうも思ったりするのです。つまり、介山は、やはり、この物語を書きながら自分自身が癒されたのだろう(作者は自分が書いた物語に癒されるものです)、そして、心の奥にある「女性嫌悪」が変化したからこそ、ユングのいう「肯定的なアニマの像」(アニマは男性の心の中にある女性像で、魂の入り口)が出現し、物語後半の女性の登場人物たちに反映されたのではないか。とくに駒井の船に乗り込んだ後のお松など、驚くほど現代的で前向きな、力強い女性像です。作者の女性嫌悪など見出せません。物語序盤で悲惨な死に方をする女性たち(お浜、お豊、お君も?)とは明らかに違います。
実は、『大菩薩峠』の最後の数巻は、私にとっては退屈で退屈で、かなり読み飛ばしました。お雪ちゃんと龍之助が小舟に乗って琵琶湖を漂っていく、実質的な「龍之助・最終回」の、あの場面は楽しく読みましたが、それが終わると、最終巻で駒井とお松がくっつくというのでそれだけを心の支えに、最後のニ、三巻を読み終えたようなものです。それにしても、あのプロポーズの言葉はいろんな意味で期待を裏切らなかった。
私は龍之助も嫌いじゃないけど、男性登場人物では駒井能登守と米友(よねとも)が好きです。女性読者を代表して(?)言わせていただくと、結婚するなら、一緒にいるといつ殺されるか分からない龍之助より、絶対、駒井甚三郎でしょうよっ!! 元殿様で、水もしたたる美男子、頭がよく進歩的で、優しくまじめな性格、それでいて自分で船を作って大海原に乗り出しちゃったりして、一緒にいて退屈しない。しかし、絵に描いたようなイケメンだからでしょうか(笑)、『果てもない道中記』ではあまり取り上げられていませんでしたが。
(こちらに続きます→「「日本の文化の三層」と、「受け身と消極」のヒーロー」)
Tweet